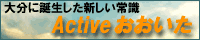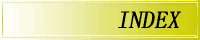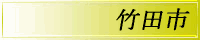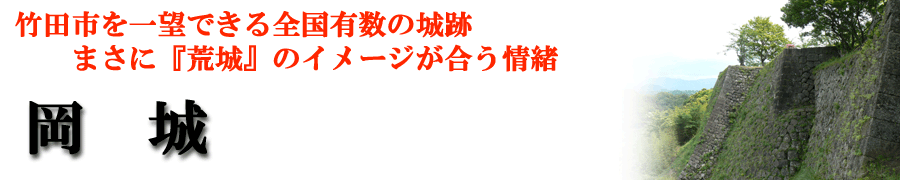
 岡城の歴史について、参考になりましたか?
岡城の歴史について、参考になりましたか?ここまで大手門跡から西の丸→近戸門跡→賄方跡→桜馬場跡と、時計回りに回ってきました。正式な岡城散策ルートは実はこの逆で、本丸方面から先に見学した方が効率が良い様です。ご注意下さい。
そしていよいよ、我々は本丸跡へと進みます。左の写真は籾倉跡の横を通る道。こんな大きな道があるわけですから、岡城のダイナミックな内部が分かります。
 西中仕切跡まで来ると、突出した石垣が目に入り、ここが岡城の情景のうち、最も有名な角度である事が分かります。
ちょうど駐車場の位置から見える風景のアップバージョンですね。石垣の勇壮な姿、その下の断崖絶壁…夜になりこの石垣のすぐ上に月が見えたりすると、それこそ「荒城の月」を口ずさみたくなるような雰囲気になるのでしょう。
西中仕切跡まで来ると、突出した石垣が目に入り、ここが岡城の情景のうち、最も有名な角度である事が分かります。
ちょうど駐車場の位置から見える風景のアップバージョンですね。石垣の勇壮な姿、その下の断崖絶壁…夜になりこの石垣のすぐ上に月が見えたりすると、それこそ「荒城の月」を口ずさみたくなるような雰囲気になるのでしょう。ここから少し小高い丘の上が本丸なのですが、慌てずに二の丸・三の丸方面を歩いていきましょう。
 岡城の城郭はほぼ東西に伸びる台地上に展開する山城なのですが、本丸・二の丸・三の丸は平山城的殿舎で構成された曲輪となっています。本丸よりも一段低い位置にあった二の丸と三の丸は、本丸共東西の仕切りによって区切られていたそうです。
岡城の城郭はほぼ東西に伸びる台地上に展開する山城なのですが、本丸・二の丸・三の丸は平山城的殿舎で構成された曲輪となっています。本丸よりも一段低い位置にあった二の丸と三の丸は、本丸共東西の仕切りによって区切られていたそうです。手前に位置する三の丸は使者の間・小姓の詰所・などと三十畳の広間の存在が確認されており、藩主の執務が中心的に行われたと考えられています。
一方、二の丸は数寄屋(和歌や茶、生け花などを楽しむ)や月見櫓があったことからも、遊興的な曲輪であったと考えられています。



 二の丸跡には、滝廉太郎を偲ぶ銅像が飾られています。実はこの像の作者は大分県を代表する世界の彫刻家・朝倉文夫氏。滝廉太郎と朝倉文夫は同窓で顔見知りだったのです。
二の丸跡には、滝廉太郎を偲ぶ銅像が飾られています。実はこの像の作者は大分県を代表する世界の彫刻家・朝倉文夫氏。滝廉太郎と朝倉文夫は同窓で顔見知りだったのです。この二の丸跡には、空井戸も存在し、明治元年の調査では横穴も確認されたそうです。現在は井戸の深さも当時の半分ほどとなり、横穴の存在が確認できていません。
とにかく二の丸跡はそこから見える風景に圧倒されます。東に地獄谷、西に清水谷。どこを見ても断崖絶壁の上に立ち、高所恐怖症の人には絶対にお薦めできないスポットw
国道57号線もしっかりと見えますので、遠目でも構いませんので、覗いてみてください。



 本丸跡は思っていたよりも遥かに広いスペースでした。現在では「岡城天満神社」なども建てられ、ひっそりとしている空間ですが、西側には三重櫓の跡も見られ、当時を偲ばせます。
本丸跡は思っていたよりも遥かに広いスペースでした。現在では「岡城天満神社」なども建てられ、ひっそりとしている空間ですが、西側には三重櫓の跡も見られ、当時を偲ばせます。天守にあたる三重櫓があるこの本丸は、もちろん城主(藩主)の居住地として利用されてきました。門の場所にはしっかりと車敷も残っていますし、門の隣には小さな扉があっただろうと思われる跡も確認できました。
さらにこの西側には道が続き、清水門跡、御廟跡、下原門跡を見ることが出来ます。
 『日本の100名城』はもちろん、『日本三大険城』『日本の音100選』など、様々な部門で賞賛を浴び続ける岡城。
『日本の100名城』はもちろん、『日本三大険城』『日本の音100選』など、様々な部門で賞賛を浴び続ける岡城。秋になると紅葉で賑わいますが、有名なのは何と言っても春の桜。その優雅さは『日本さくら名所100選』にも選定されるほど。毎年4月の上旬にはこの桜の満開の中、雅な大名行列が行き交う、『岡城桜まつり』が開催され、多くの観光客で賑わいます。
各地の荒廃したお城で、復興を望む声が多い中、この岡城だけは荒れ果てた石垣城のイメージが最も良く合う様な気もしませんか?
『荒城』
このイメージがこれほどピッタリと合うお城も他にないと思います。
参考資料:入城の際貰える絵巻風案内用紙(入場料に含まれています)