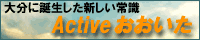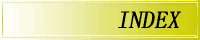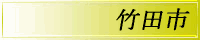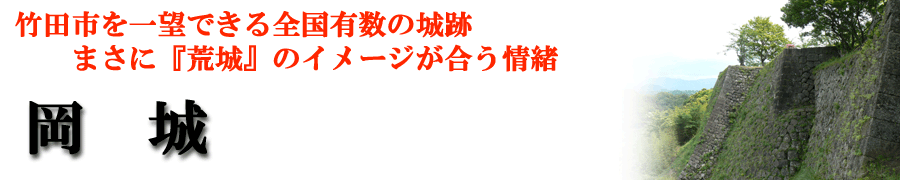
 竹田市のシンボルと言えば、この岡城を置いて他は語る事は出来ません。
竹田市のシンボルと言えば、この岡城を置いて他は語る事は出来ません。天守は存在しないにも関わらず、お城マニアをも唸らせる岡城の魅力に迫るべく、2007年5月、我々は竹田市へと行ってきました。今回は岡城をぐるっと一周しながら、岡城を取り巻いてきた歴史を勉強してみたいと思います。
岡城へのアクセスはどこから来ても、竹田市内を通って坂道を登るこのコースしかありません。駐車場は野球場もびっくりの巨大スペース。ここには岡城会館という食事・お土産スポットもあり、休日や観光シーズンには大いに賑わいます。
 まずはこの受付で入城料を支払います。入城料は300円ですが、決して高いとは感じません。
何故ならこの入城料と引き換えに、案内図を貰えるからです。「そんなの普通じゃん」と思うことなかれ!岡城のこの案内図は普通ではありません。読み応えのある巻物になっていて、紙自体もペラペラではなく、非常に重量感があります。
必ず満足の行く手土産・記念品になることでしょう。
まずはこの受付で入城料を支払います。入城料は300円ですが、決して高いとは感じません。
何故ならこの入城料と引き換えに、案内図を貰えるからです。「そんなの普通じゃん」と思うことなかれ!岡城のこの案内図は普通ではありません。読み応えのある巻物になっていて、紙自体もペラペラではなく、非常に重量感があります。
必ず満足の行く手土産・記念品になることでしょう。そこから岡城への入り口まで約100mそこそこ。途中茶屋などを通り、胸を躍らせながら歩いていきましょう。



 岡城址は国指定史跡に登録されています。その登録年月は昭和11年の12月。その古さから考えても、国が最優先で保護しようとした重要な史跡である事が窺えます。
岡城址は国指定史跡に登録されています。その登録年月は昭和11年の12月。その古さから考えても、国が最優先で保護しようとした重要な史跡である事が窺えます。ここから大手門まで、歩いて5分弱ほどの坂道・階段が続きます。何と言っても特徴的なのはこの広い石畳。巨人の階段の様にも見えませんか?この石塁を登っていくにつれ、徐々に景観が開けていく事も楽しみの一つですから注目してください。


 そしていよいよ大手門跡へと辿り着きます。
そしていよいよ大手門跡へと辿り着きます。岡城の大手門は、そもそも城の東側にありました。しかし、1613年(慶長18年)に西側のこの位置に移されています。その理由は、朝日が眩しかったからだそうです。 またこの大手門の移転には、あの加藤清正公の意見が採用されたという説もあります。
良く見ると、しっかりと城門の車敷も残されており、時代を感じさせない貴重な跡です。


 大手門跡から入って真っ直ぐ歩くと、東側の端に旧大手門跡もちゃんと残っています。これはこれで良く残っているな、と感心できます。
大手門跡から入って真っ直ぐ歩くと、東側の端に旧大手門跡もちゃんと残っています。これはこれで良く残っているな、と感心できます。城中への出入りは、厳しい管理体制が敷かれていたそうで、主な門には全て門番が置かれ、出入りの監視が行われていたそうです。ちなみに門は通常、朝六時に開き、夕方六時に閉まっていたそうですよ。
では次のページから具体的に岡城の歴史について、お話しましょう。