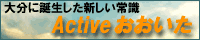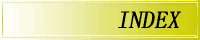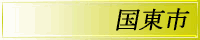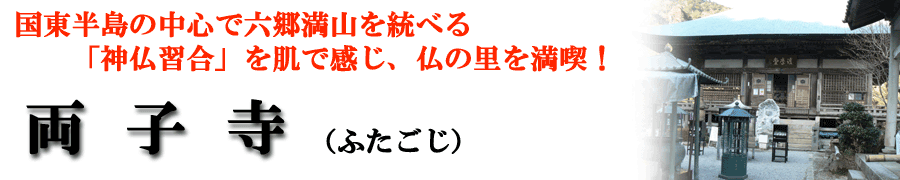
 護摩堂を後にし、両子山方面へと歩を進めると、見た事のあるような光景を目にします。
護摩堂を後にし、両子山方面へと歩を進めると、見た事のあるような光景を目にします。右側に商売の神様「稲荷堂」が見えるこのアングルは、秋になると紅葉のベストショットとして、様々場面で良く見かけます。四季折々の景観が楽しめるのも、この両子寺の素晴らしさですよね。
ここからさらに真っ直ぐ奥へと進めば、「国東塔」「百体羅漢」そして「両子山」といった数々の名所が待っています。しかし今回は時間の都合もあり、断念。ここから右手へ川を渡り、「大講堂」を目指しました。
 大講堂に辿り着くのに、そう時間は掛かりません。10m四方の正方形で、実に720本の垂木を使用しています。
大講堂に辿り着くのに、そう時間は掛かりません。10m四方の正方形で、実に720本の垂木を使用しています。すぐに気が付くのはその新しさ。実は大講堂は平成3年に建てられたばかり。明治維新の廃仏毀釈の法難で焼失したそうです。
この中には、県指定の有形文化財「木造阿弥陀如来坐像」が祀られています。その勇壮さは威厳を感じるのに申し分なく、願い事がなくとも、思わず両手を合わせてしまいます。
 実は両子寺には、我々の興味をそそる『七不思議』なるものが存在します。
実は両子寺には、我々の興味をそそる『七不思議』なるものが存在します。この写真は七不思議の一つ、「しぐれ紅葉」。
両子寺の境内にあるこの紅葉の下に立ち、上を見上げると、晴天の日でもしずくが落ちると言われています。
この七不思議に関しては、また別の機会に検証してみるとしましょう。
両子寺の魅力が皆さんに伝わったでしょうか?
まだまだ多くの見所がありますので、次回はまた別の目的で来てみたいと思っています。
しかし!
これだけで両子寺を後にするのは、非常にナンセンスです。そう!両子寺のシンボルとも言うべき、あの写真を撮らなければいけません。
 その場所は、両子寺の入り口付近にあります。一番上まで車で来た方なら、一旦車に乗り込み、戻る必要があります。
その場所は、両子寺の入り口付近にあります。一番上まで車で来た方なら、一旦車に乗り込み、戻る必要があります。真っ赤な「無明橋」の傍、山門が見渡せるその入り口に彼らは文字通り仁王立ちしていました。
これが有名な両子寺の「仁王像」。
問答無用な姿は、訪れる者を安心させ、また威厳ある姿に、感動すら覚えるはずです。




神仏習合の象徴・六郷満山の中枢・両子山の麓から、1300年以上もの間、国東半島を見守る仁王像。
一体どれだけの歴史を目撃し、どれだけの人々を見てきたのですしょうか?
両子寺で、ふと目を瞑ってみました。自分が今いるのは、国東半島に中心だと思うと、より感慨深くなります。
そのまま何気なく、周りの匂いを嗅いでみました。自分が吸っている空気は1300年前の空気かもしれないと思えました。
不思議な感覚さえ感じる事のできる、足曳山 両子寺。
国東市の誇りであり、大分県の歴史を誰よりも知る、貴重な文化財です。